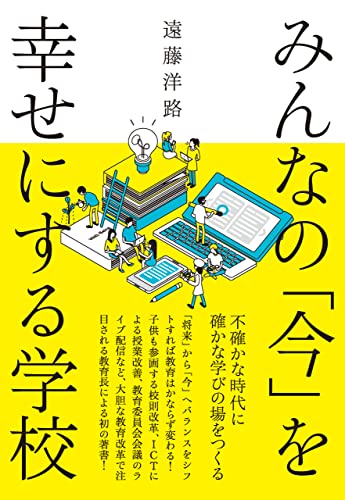ここ2~3年で,「総合的な英語力」という用語が(主に大学英語入試に関わる文書の中で)頻繁に用いられるようになってきた。世間の認知度も低いし,英語教育に関係する専門家の間でもほとんど話題になっていないと思うが,明らかな傾向としてそう言える。現在,「総合的な英語力」という用語が大学英語入試政策の中で表出した経緯とその動向について分析しているが(順調にいけば,夏ごろに論文が公開される予定),ここではその前段階として,「総合的な英語力」とは一体何なのか,どのような学術的知見にもとづく用語なのかについて整理しておきたい。
1. ここ2~3年で(地味に)多用されている「総合的な英語力」
大学英語入試改革のキーワードと言えば,従来までは「4技能」と言えるだろう。「これまでの入試はリーディングとリスニングの2技能に特化していた。だから日本人は話すことと書くことができないんだ。ってことで,大学入試を4技能化しよう! 英検やTOEFLなどの資格・検定試験を活用しよう! そうすれば,高校の英語教育が劇的に変わる! 日本人みんな英語がもっと話せるようになる!」というあまりにも杜撰で乱暴な論理で進められたのが2020年度の大学英語入試改革であった。「4技能」というマジックワードがもたらす推進力はいまだに健在で,それこそつい先日,鈴木寛さんのインタビュー記事 (L) でも上記と同様の論理で入試改革の必要性が訴えられていた。本記事の主旨からは逸れるので簡潔なコメントだけ残しておくとすれば,いい加減,入試を魔法の杖として扱うのはもうやめようよ…… 「地域間、学校間、生徒間の格差が目立っているのも事実だ」と認めているにもかかわらず,なぜ共通テストに4技能型の資格・検定試験を導入することが「日本人全体が英語コミュニケーション能力を高めるチャンス」(下線は引用者)と言い切れるのか,この人の思考が全く理解できない。この「日本人全体」の中には,共通テストを入試で使用しない高校生の存在や,大学へ進学しない高校生の存在が排除されているのではないか。そもそも,教育現場の実態も苦労もよく考えないまま,入試さえ変えれば高校の英語教育が劇的に良くなるというあまりにも素朴な因果推論をしていることに心底あきれる。誤解しないでいただきたいのが,別に今の入試に欠点がないと言いたいわけではない。私が言いたいのは,入試政策以外にもやらないといけないことは山ほどあるわけで,現状の問題・課題をすべて入試に押し付け,他の施策については思考停止を促すような提言はやめていただきたい,ということ。
閑話休題。タイトルにもあるように,ここ2~3年で「4技能」と並んで多用されている用語が「総合的な英語力」である。この用語が特徴的に使用されているのが「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」(L) である。以下に令和6年度と令和7年度の一部を引用するので,両者を見比べてみていただきたい:
<令和6年度版>
高等学校学習指導要領では,外国語の音声や語彙,表現,文法,言語の働きなどの知識を,実際のコミュニケーションにおいて,目的や場面,状況などに応じて適切に活用できる技能を身に付けるようにすることを目標としていることを踏まえて,4技能のうち「読むこと」「聞くこと」の中でこれらの知識が活用できるかを評価する。したがって,発音,アクセント,語句整序などを単独で問う問題は作成しないこととする。(大学入試センター, 2022, p. 4, 下線は引用者)
<令和7年度版>
⾼⼤接続改⾰の中で,⾼等学校学習指導要領の趣旨を踏まえ,各⼤学の個別選抜や総合型選抜等を含む⼤学⼊学者選抜全体において,「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の総合的な英語⼒を評価することが求められている。(大学入試センター, 2023, p. 7, 下線は引用者)
どちらの文書も趣旨は類似しているが,令和6年度では「4技能」が使用されていたのに対し,令和7年度では「4技能」が使用されていないことに加えて,「総合的な英語力」が新出している点に注意されたい。些細な違いに思うかもしれないが,この特徴は偶然ではなく,文書作成者の明らかな意図を感じる。というのも,令和7年度の問題作成方針では,文書全体にわたって「4技能」という用語が一切使用されていないからだ。それだけでなく,2023年末に公開された,「令和7年度試験の問題作成の方向性、試作問題等」(L) の中でも,「4技能」という用語は一度も使用されていない一方で,「総合的な英語力」は多用されている。
2. 「総合的な英語力」という用語が生まれた経緯
では,「総合的な英語力」という用語は一体どこからやって来たのか? その起源は2020年から2021年にかけて開かれた「大学入試改革のあり方に関する検討会議」にある。詳細は省くが(夏公開予定の論文を参照),当会議にて複数の委員により「英語4技能」という概念の妥当性・正当性が論点として挙げられた。具体的には,英語能力を4技能に切り分けて別々に評価・育成する方針に対して委員の半数以上が疑義を示し,そのアンチテーゼとして,委員の一人である上智大学の渡部良典教授が「総合的な英語力」「インテグレーティッドスキル」を提示したところ,他の委員にも賛同を示し,最終的に2021年7月に公開された「大学入試のあり方に関する検討会議 提言」(L) に反映された。
「大学入試のあり方に関する検討会議 提言」は以下の5章構成となっている:
第1章 大学入学者選抜のあり方と改善の方向性
第2章 記述式問題の出題のあり方
第3章 総合的な英語力の育成・評価のあり方
第4章 地理的・経済的事情、生涯のある受験生への合理的配慮等への対応
第5章 ウィズコロナ・ポストコロナ時代の大学入学者選抜
「総合的な英語力」についての説明に1章分を割いていることから,この用語の生成を当会議の成果の一つとして重視している点が読み取れる。なお,こちらの資料についても「4技能」という用語が一切使用されていない点も強調しておきたい。
ところで,ここまで定義せずに使用してきたが,「総合的な英語力」とはいったい何なのか。「大学入試のあり方に関する検討会議 提言」では次のように説明されている:
なお、「読む」、「書く」、「聞く」、「話す」の各技能は、それぞれ別々に育成されるものではなく、例えば「聞いた情報を整理して自分の考えを話す」、「自分の考えを書くために必要な情報を読む」といった、技能統合的な言語活動を通して、総合的に育成・評価するべきものであり、その観点から、本提言では「総合的な英語力」という表現を使うこととする。(p. 19)
言わんとすることはわからなくもないが,これだけの説明では曖昧過ぎる。どのようなテストであれば「総合的な英語力」を評価することになるのかが全く不明である。提言の中には,共通テストの規模で「総合的な英語力」を評価することは実施上の課題が大きいことを理由に,「多くの大学・学部にとっては、資格・検定試験の活用が現実的な選択肢となる」(p. 26) という記述がある。言うまでもなく,「資格・検定試験」にも色々あるわけで,その目的もレベルもだいぶ違う。すべてを一括りにして「資格・検定試験ならば,総合的な英語力が測れる」という横暴な論理が今後展開されないことを切に願う*1。
また,「総合的」とは言うものの,以下のような説明からもわかる通り,そこには従来のスピーキング・ライティングの育成・評価の推進という意味が込められている点も注意が必要である:
高等学校までの教育課程においては、総合的な英語力の育成が目標とされ、授業を実際のコミュニケーションの場面とする観点から高等学校学習指導要領で「英語で授業を行う」と告示されてから10 年以上が経過している。一方、大学入学者選抜が「読む」ことの力や文法等の知識を問うことが多いため、大学入学者選抜が近づくほどに、「話す」、「書く」を含めた総合的な英語力の育成より、「読む」ことの力や文法等の知識に関する学習に偏る傾向を生んできたのではないかとの指摘が多い。(p. 25)
結局のところ,「4技能」の論法と同じではないか…… と感じるのは私だけではないだろう。「総合的な英語力」という用語自体に罪はないであろうが,この用語が提示された当初の意味からどんどん離れて行っているようにしか見えない。
3. 応用言語学,テスト研究の知見から
そもそも,提案者は「総合的な英語力」という用語にどのような意味を込めていたのか。「総合的な英語力」に関する学術的知見はどれほど蓄積しているのか。この点について,応用言語学,テスト研究の知見を概観しながら最後に整理しておきたい。
integrated skill の研究の特徴
integrated skill 関連の先行研究を概観してみたところ,印象としては,特に「ライティング」関連の研究が多い印象。すなわち,「書くために読む/聞く」とか「書くときと読む/聞くときの認知スキルの差異」とかの研究が多かった。この分野は専門ではないため,あくまで片っ端から先行研究を読んだところの印象ではあったが,Huang & Hung (2018) でも「大半のintegrated test tasks に関する研究はライティングに着目していて,スピーキングに注目した研究はほとんどない」(p. 202) とはっきり書いてくれているので,たぶん当たっているのだろう。
integrated assessment に関する用語の横溢
先の「大学入試のあり方に関する検討会議」では「総合的な英語力」「インテグレーティッド・スキル」という呼び名が使われている一方で,応用言語学ではどちらかといえば,"integrated task" や "integrated assessment" という用語の方を多く目にする印象。しかしYu (2013) によれば,ほぼ同一内容を指すにもかかわらずこれ以外にも複数の呼び名があり,用語の横溢が混乱を招いているらしい。細かい用語の違いから挙げれば,"integrated skills" と表記する文献もあれば,"integrated competence" と表記する文献もあったなぁと。 あるいは,integrative test なのか integrated assessment なのか。この点については,Yu (2013) で検討されている。昔から存在するのは integrative test で,彼によれば,「言語技能の一要素に注目していないテスト (not discrete-point test)」「さまざまなスキルを組み合わせることが求められるテスト」(p. 112) という定義で,その例としてクローズテスト (cloze test) が挙げられている。クローズテストとは,一部が空欄になった文章を穴埋めすることが求められるテストで,なぜそれが "integrative test" なのかと言えば,"both linguistic knowledge and the ability to predict meaning from a written text" だから——とのこと。なるほど,複数の認知スキルが統合されることが求められていれば,integrated test と呼べるということであろう。一方で,言語技能の「統合 (integrated-ness)」には,上記のようなミクロな認知スキルの「統合」以外に,リーディング・リスニング・ライティング・スピーキングのようなマクロな言語技能の「統合」を意味することもあり,integrated assessment は後者の場合に用いられるのが主流のようだ (Yu, 2013, p. 113)。この区分に従えば,「大学入試のあり方に関する検討会議」で提唱された「総合的な英語力」は,後者の integrated assessment に近い概念であると言えるだろう。
ただし,両者の定義は研究者間でも違いがあり,それぞれの用語がどちらの意味で使用されているのか曖昧なこともあれば混同されている場合もあることに加え,両者の位置づけについても不明瞭な点が多い(ex. integrated assessment をintegrative test と同義として扱うか,あるいは,下位概念として扱うか等)。integrated assessment の合意可能性が求められる所以である。
上記は skill / competence,test / assessment をめぐる言ってしまえば細かな違いだが,そもそもの名称がまったく異なる呼び名が複数ある点もこの分野の合意可能性を阻害している。Yu (2013) は"integrated assessment" と同義の用語の例として,"discourse synthesis, summary writing or summarization, integrated writing, writing from source(s), reading-writing task, writing-from-readings, and reading-responsible writing task (just to name a few)" (p. 113) を挙げている。
integrated assessment の意義と課題
Language Asessment Quarterly でIntegrated Writing Assessment が特集された際に,Cumming (2013) はその総括として,integrated writing assessment を行うに当たる5つの有用性 (promises) と5つの危険性 (peril) を提示している (p. 2)。
5つの有用性:
- 現実的でやりがいのある読み書き活動を提供する
- 受験生が具体的な内容についてライティング活動を行う
- 従来の技能分離型に関連する試験方法または練習の効果に対抗する
- 構築–統合モデル (construction-intengration model) あるいはマルチリテラシーモデルに沿って言語能力を評価する
- 指導や自己評価のための診断的価値を提供する
※ 1つ目については真正性 (authenticity) とも言い換えられるであろう
5つの危険性:
- 作文能力と資料理を理解する能力の測定を混同する
- 評価と診断を混同する
- 定義が曖昧で,それゆえに採点が困難な分野を含む
- 実力を発揮するためにはある一定以上の能力が必要であり,異なる能力レベル間で系統立てて比較できない
- ライティングのソースにした文章と,受験者自身が生成した文章の区別の困難さ
※ 4つ目について補足しておくと,要するに「書くために読む」という活動をする際に,そもそも「読む」能力が一定水準以上に達していないと「書く」までたどり着くことができないわけで,そのテスト結果の善し悪しで果たして「書く能力がある/ない」と言えるのか,一体何を評価していると言えるのか,という指摘。
「大学入試のあり方に関する検討会議」で「総合的な英語力」が推進された理由は,議事録を見た限りでは真正性の追求が大きい。確かに大学での英語を使った講義や,社会人として英語を使用する場面を想定してみると,4技能をそれぞれで分離して使用するよりも,「書くために読む」や「話すために聞く」といった言語技能の統合の場面が連想されることは私だけではないだろう。しかし,Comming も警告するように,その定義がきわめて曖昧であることは否定できず,定義が曖昧であればそのテストの妥当性や信頼性にも不安を禁じ得ない。単なる診断テストとして日ごろの指導・学習に活かすために行うならまだしも,果たしてそれを入試というハイステークス場で実施するに耐えるだけのテスト設計が可能なのだろうか。個々の教員が教室レベルで評価を行うならまだしも,果たしてそれを共通テストほどの大規模なテストで評価するだけの知見とリソースが用意されているのだろうか(もっといえば,そのコストに見合うだけの価値がそこにあるのだろうか)。
中途半端な形で終わってしまいましたが,つづきは論文で書く予定なので,興味のある方はそちらをお読みいただければ幸いです。
本投稿と夏公開予定の論文を通じて,2024年度新課程の大学英語入試に関する方針について,一考を促す材料を提供したいと思います。
*1:願ってはいるものの,実際のところは…… という話についても夏公開予定の論文で言及する予定です